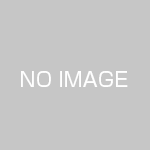このたび国際司法裁判所(ICJ)が、国家が過去および現在の温室効果ガス排出に伴う被害に対して責任を負うとし、その違反が国際的に不法な行為となる可能性を明確にしました。これにより、被害を受けた国や将来世代が賠償や行為の停止を求める道が開かれたことは、気候正義にとって歴史的な転換点といえます。この画期的な諮問意見に対して強く支持いたします。
学術界においても同様の流れが強まっており、Nature 誌などでは化石燃料企業の温室効果ガス排出と極端気象の損害を企業単位で定量化する研究が発表され、オーストラリアや米国などの主要資源企業の排出が数千億ドルから数兆ドル規模の損害を生み出したとする分析も示されています。さらに、最富裕層の排出が気候変動に不均衡に大きな影響を与えていることも明らかになり、法的・政策的責任の分担を求める学術的根拠が急速に整備されつつあります。
こうした背景を踏まえ、企業や政府にはライフサイクルアセスメント(LCA)に基づき製品やサービス全体の環境影響を定量的に把握し削減計画を策定・公開すること、特に温室効果ガス多排出産業には気候変動による損失と損害を認識し補償制度を検討すること、政府には排出目標と達成状況を透明に示しつつ脱炭素インフラへの投資や技術導入支援を強化すること、そして消費者には日常の消費行動や生活様式が強く気候変動と関わっていることを理解して脱炭素社会に向けた行動変容を速やかに行うことが求められます。
私はこれまでLCA研究に携わる者のひとりとして、ライフサイクル全体を通じて環境影響を削減するための科学的基盤を日本企業とともに築くための研究をしてきましたが、今回のICJ判決と学術界による警鐘は、この活動の意義をさらに強固なものとするものと認識します。SPEED研究会は今後もサステナブル経営とエコイノベーションを推進し、国際社会と連携して持続可能な未来の実現に取り組んでいきます。
2025年9月5日
SPEED研究会 会長
伊坪徳宏